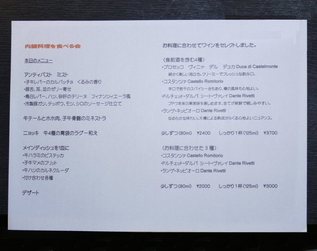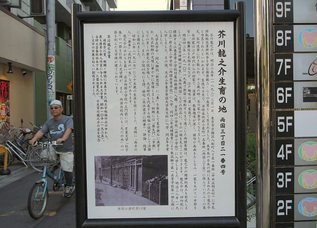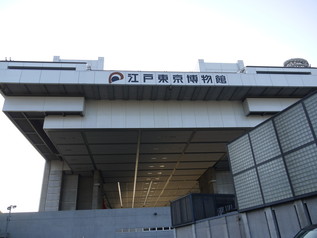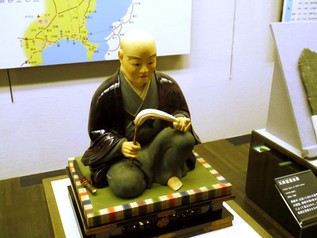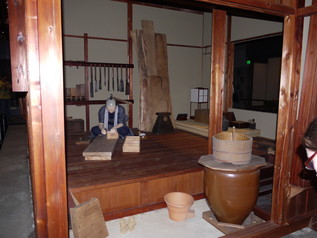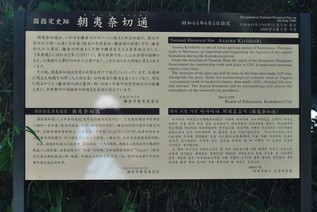2010.08.27
清里高原バス旅行・・・(旅行)
昨日(木)、日帰りのバス旅行で清里高原に行ってきました。
旅行の前日(水)の夜の8時には、私は行くことになっているとは思っていませんでした。
家内が近所の仲の良い奥さんと行くのだろうと思っていて、明日○○さんと清里に行くのは朝が早いのだろうと話しかけたら、家内があなたと二人で行くのよと言います。
えー、俺も行くのかと私。まぁー、日帰りだし、準備はバッグにタオル地の汗拭きハンカチとカメラを入れるぐらいです。
そんな事情で、主に「ユリとヒマワリ」の花を見るバス旅行に出かけました。
バスは朝の7時50分に横浜の天理ビルの前から出発です。朝食用に横浜地下街の売店でおにぎりなどを買い、天理ビル前への階段を上ってゆくと、人が集まっています。色々なコースのバスが出ます。旅行会社の添乗員が、何人も立っていて、それぞれのコースに分かれてバッチを配り、乗るバスを告げています。
いよいよ出発です。今回のバス旅行では、バスガイドは居ませんが、美人添乗員がいます。
横浜を出発して、調布インターで中央高速に乗るまで渋滞で手間取りながらも、その後は快適に走ります。小仏峠トンネル、相模湖、上野原と、昨年歩いた甲州街道が頭をよぎります。そして、街道歩きで立ち寄った「談合坂パーキングエリア」が1回目のトイレ休憩でした。パーキングエリアも背面の入り口から入って昼食を取った時と違って見えます。 また、サービスエリアと高速道路を挟んだ反対側の崖下には、いまだに江戸期の雰囲気が漂う野田尻宿がひっそりと佇んでいるのを知る人はほとんどいないことでしょう。
休憩の後は、笹子トンネルを抜けて「小淵沢インター」まで一気に走り、八ケ岳高原ラインを進んで「八ヶ岳チーズケーキ工房」に着きました。入り口で楊枝に刺した小さな試食のチーズケーキをもらい売り場に入って行きトイレで用を足します。
チーズケーキ工房を後にして、ハイランドパークに向かい、ここで昼食のバイキングです。ここは、冬はスキー場なのでリフトが二本あり、一つはパノラマリフトと呼ばれていて、10分で一気に1900mまで上ります。 天気の良い日は南アルプスから富士山まで一望できるらしいのですが、今日は晴れてはいても雲が多く見ることはできません。 もう一つはフラワーリフトと呼んでいて、片道5分ですが、ユリの花やその他の花々を見ることができます。我々は、フラワーリフトを選んで、ユリの花を撮影してきました。
最初は、ユリの花など咲いていないではないかと思っていたら、中ごろを過ぎると足下に色とりどりのユリが見えてきました。
暑い日が続いていても確実に季節は巡っていて、駐車場脇にはコスモスの花が風に揺れていました。
2時間ほどハイランドパークで過ごし、次の目的地の「明野のヒマワリ」を見に行きます。日帰り温泉施設もあり、美しく整地されています。
この辺りは、日本で一番日照時間が多いところといわれ、広いヒマワリ畑があり、映画の場面にもたびたび使われたとのことですが、私は、ソフィアローレンのヒマワリが頭に浮かびました。
残念ながら、ヒマワリは既に盛りを過ぎて、メインの畑はもう花びらを落としていましたが、幾つかのサブの畑はまだ鑑賞することができる状態でした。
到着して撮られた集合写真を直ちにプリントアウトして、商魂たくましく駐車しているバスのところまで、おじさんが来ています。デジカメで撮ってプリンターで打ち出すので直ぐにできて、直ちに売れるのですね。添乗員さんが、困っているように見えます。
バス旅行の常として次々と新しいところを求めて駆けまわります。
次は、枝豆の収穫体験です。400gぐらい入るとの小さなビニール袋を貰って、皆で畑で枝豆を摘みます。子供たちには楽しい体験です。
日もだいぶ傾いてきました。韮崎のインターで中央高速に乗り勝沼まで走って、トイレ休憩を兼ねてワイナリーの「シャトー勝沼」に寄ります。ワインは試飲させてくれますが、皆さん些か疲れ気味です。
ワイナリーで終わりかと思っていたら、もう一箇所「昇谷」という名のキムチの直売所に寄りました。口上のうまさに思わずキムチを買ってしまいました。

とっぷりと、日が暮れました。八王子の石川サービスエリアです。あとは新横浜を通って横浜です。
安い料金で一日たっぷり楽しませてくれました。